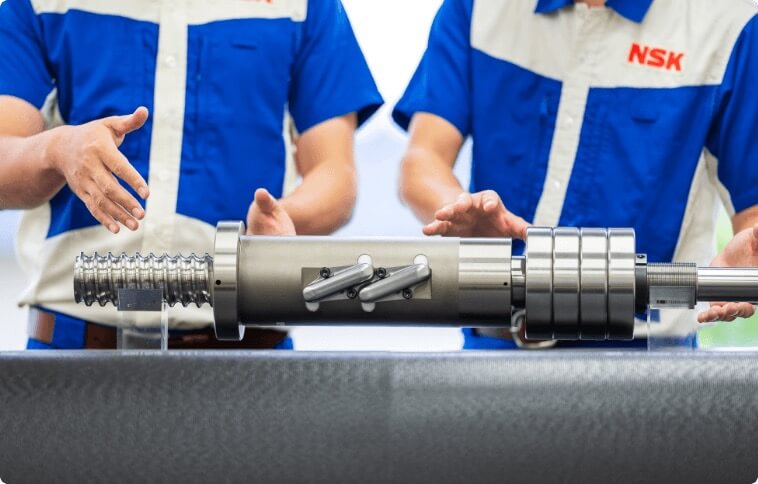Vol. 3
データドリブンで拓くNSKの未来
デジタル変革本部 データドリブン企画推進部
Vol. 3
データドリブンで拓くNSKの未来
デジタル変革本部 データドリブン企画推進部
チームメンバー
-
 部長Tさんキャリア入社2021年にキャリア採用で入社。前職は、コンサルティングファームでDX、BPR、グローバルERP導入、ガバナンス強化などに従事。NSKでは、DX推進計画の策定とデジタル変革組織の立ち上げを実施後、全社的なチェンジマネジメントやデジタル人材育成、AI活用推進などを担う。2024年よりデータドリブン企画推進部の部長として、NSKのデータドリブンへの変革に向けた様々な取り組みを推進中。
部長Tさんキャリア入社2021年にキャリア採用で入社。前職は、コンサルティングファームでDX、BPR、グローバルERP導入、ガバナンス強化などに従事。NSKでは、DX推進計画の策定とデジタル変革組織の立ち上げを実施後、全社的なチェンジマネジメントやデジタル人材育成、AI活用推進などを担う。2024年よりデータドリブン企画推進部の部長として、NSKのデータドリブンへの変革に向けた様々な取り組みを推進中。 -
 グループマネジャーMさんキャリア入社2019年にキャリア採用で入社。前職は、システム会社で製造業向けの設計システムや受注システムの開発・運用保守に従事。NSK入社後、技術部のシステム運用保守を経て、デジタル変革本部へ異動。これまでの経験で培った「既存の仕組みを読み解く力」を生かし、現在は生産・技術・事業領域における課題特定、データ活用支援などに取り組む。TさんからのコメントCommentMさんは、大企業が故に縦割りになりがちな社内で、部門間連携をうまく取りつつ、課題解決に取り組んでいます。前職で培ったシステム開発・運用の経験から、現場の視点を大切にしたアプローチが得意で、関係者との調整にも長けています。新しい技術や業務領域に対する好奇心が強く、初めての領域にもモチベーション高く取り組んでくれるところに頼もしさを感じています。
グループマネジャーMさんキャリア入社2019年にキャリア採用で入社。前職は、システム会社で製造業向けの設計システムや受注システムの開発・運用保守に従事。NSK入社後、技術部のシステム運用保守を経て、デジタル変革本部へ異動。これまでの経験で培った「既存の仕組みを読み解く力」を生かし、現在は生産・技術・事業領域における課題特定、データ活用支援などに取り組む。TさんからのコメントCommentMさんは、大企業が故に縦割りになりがちな社内で、部門間連携をうまく取りつつ、課題解決に取り組んでいます。前職で培ったシステム開発・運用の経験から、現場の視点を大切にしたアプローチが得意で、関係者との調整にも長けています。新しい技術や業務領域に対する好奇心が強く、初めての領域にもモチベーション高く取り組んでくれるところに頼もしさを感じています。 -
 データエンジニアOさんキャリア入社2022年にキャリア採用で入社。前職では、プログラマとしてシステム開発・運用保守、業務効率化支援、社内システム導入に従事。法務・人事領域のデジタル化に携わった後、現場主導によるDX活動の立ち上げに参画。現在は財務・管理領域を中心に、データ基盤整備、BIツールの開発・支援、データ活用人材の育成などに取り組む。プログラミングやデジタルツールの導入と普及、新しい取り組みの立ち上げが得意。TさんからのコメントCommentOさんは、バランス感覚が良い方です。組織を横断した業務や、ステークホルダーマネジメントが複雑なプロジェクトであっても、柔軟に対応しながら最適なソリューションを提案できるのが強みだと感じています。業務の整理から実装まで一貫して進める姿勢は、チームにとっても大きな支えとなっています。
データエンジニアOさんキャリア入社2022年にキャリア採用で入社。前職では、プログラマとしてシステム開発・運用保守、業務効率化支援、社内システム導入に従事。法務・人事領域のデジタル化に携わった後、現場主導によるDX活動の立ち上げに参画。現在は財務・管理領域を中心に、データ基盤整備、BIツールの開発・支援、データ活用人材の育成などに取り組む。プログラミングやデジタルツールの導入と普及、新しい取り組みの立ち上げが得意。TさんからのコメントCommentOさんは、バランス感覚が良い方です。組織を横断した業務や、ステークホルダーマネジメントが複雑なプロジェクトであっても、柔軟に対応しながら最適なソリューションを提案できるのが強みだと感じています。業務の整理から実装まで一貫して進める姿勢は、チームにとっても大きな支えとなっています。

社内データを最大限活用し
データドリブンな組織へ
変化の大きい近年において、全社員がデータを活用し、意思決定のスピードや精度を高めることの重要性は高まっています。データドリブン企画推進部は、データドリブン組織への変革を目指して新設されました。販売・生産・会計などの基幹システムの刷新や、主要なものづくりにおけるサプライチェーンの仕組みづくりなど、全社的なシステムプロジェクトが進んでいく中、そこから生まれる膨大なデータを活用することで、事業への貢献と付加価値の創出を目指しています。

様々なデータを活用して
課題の解決法を提案
部署の立ち上げ期は、データドリブン企画推進部の社内における認知度向上と、概念検証を中心としたデータ活用の支援を中心に活動しました。事業管理や人材管理における主要なKPIの見える化や分析支援、全社的な生成AI活用に向けたツール開発、製造現場におけるアナログ設備や非デジタル設備の見える化に向けたIoT活用プラットフォームの構築など、様々な仕組みづくりに着手。次年度以降の本格的な展開に向けた基盤を構築しました。

議論を重ね、新しい価値を社内へ導入する
どのような形で業務を進めていますか?
 Tさん
Tさん私たちは、「誰もが必要な時に、必要なデータにアクセスし、意思決定に生かせる環境をつくること」を目指しています。2024年4月に立ち上げられた部署で、各部門の保有データやその活用状況、課題などを把握することから始めました。個別に上がってきた課題は、ノーコードプラットフォームやPythonなどを活用して簡易的な分析環境を準備し、データの見える化や活用を促進しています。
 Mさん
Mさんこれまでも各部門でデータ分析を行ってきています。しかし、データ量の増加やツールの進化によって、従来の方法で十分なのか、新しい方法を取り入れることで分析の効率化や高度化を進めることができるかを確認する必要がありました。そこで、まずは各部門を訪問して、新たなデータ分析手法を体感してもらうことからスタートしました。

苦労した点、難しかった点について教えてください。
 Mさん
Mさん新たなやり方を身近に感じてもらえるよう気を配りました。新しいものが持ち込まれた際に「これ、本当に必要?」「そこまでしなくていいのでは?」といった疑問を感じるのは、ごく自然な反応と思っています。そのため、まずは非常にシンプルなサンプルツールを作成し、各部署の担当者の方と相談しながら徐々にツールを育てていくことで、少しずつ活用を促進しています。
 Oさん
Oさん各部署に新しい価値を実感してもらうために、簡単なモックアップを作成し、各部署に新しい価値を実感してもらう取り組みをしています。その過程で、各部署の業務を深く理解し、全体像を把握することが不可欠でした。業務に即した仮説を立てながら進めることで、各部署に最適な機能を見つけ出し、効果的な提案を行っています。
 Tさん
Tさん「面白そう」と関心は持たれても、実際のオペレーションに組み込んでもらうまではまだまだ距離があります。例えば、優秀な社員はこれまでの経験から様々な知見を持っていて、脳内のデータベースをもとに仕事ができてしまいます。エクセルの数字を見るだけで裏で起きている事象が予測できてしまうのです。その知見を得るためには膨大な経験を要しますが、ビジネスがかつてないスピードで変化する中で、経験の蓄積だけで不確実性に対処することはできません。情報を見える化し、未経験の領域であってもデータで補いながら意思決定していくことが必要です。

この部署の良さをどのように感じていますか?
 Mさん
Mさん意見を率直に言い合える環境を魅力に感じています。議論を重ねて相手を理解しようとする姿勢がとても強いです。異なる視点を持ち寄る場面でも、Tさんが議論の流れをうまく導いてくれ、Oさんが冷静に対応をしてくれるおかげで、チーム内の調和が取れていると感じています。
 Oさん
Oさん
年齢や職歴に関係なく、フラットな関係の中で議論が活発に行われているところです。「部としての方針はこうだから」とトップダウン的に進めるのではなく、都度メンバー内で議論を交わして答えを出しています。私としては、大学の研究室に近い雰囲気だと感じています。
情報共有のスピード感も速く、担当者が課題を握ったまま動けなくなるようなことはありません。チーム内で、まめにオンラインミーティングやチャットで情報共有をしています。


チームメンバーのどのようなところに助けられていますか?
 Tさん
Tさんポジションにかかわらず、自分で考えて行動し、自発的に仕事に取り組めるチームなので、私が細かく指示を出す必要がありません。また、日々新しい情報を取り入れながら方向性を調整する必要がありますが、状況に応じた方針転換にも素早く対応してくれるなど、柔軟性の高さに助かっています。
 Mさん
Mさんこのチームでは、日々新しいインプットがありますし、私が今持っている視座では足りない部分を常に指摘してもらっています。新しい経験をしつつ、高い目標に向けて日々成長させてもらっていることに対して感謝しています。
 Oさん
Oさん私は技術や課題設定などは得意ですが、ステークホルダーを集めてプロジェクトを推進するのはまだまだ未熟です。しかし、TさんとMさんがその部分をカバーしてくれるので、自分の役割に集中できるのがありがたいですね。


NSKでDXに取り組む魅力を教えてください。
 Mさん
Mさんデータ分析には「高度な統計知識が必要」と思われがちですが、NSKはこれから本格的に仕組みを作り上げていくフェーズです。今大事なのは、それぞれの部署の業務を理解して、データをどう生かすかを考える力です。高度なテックスキルを身につけていなければならないということはないので、多様なスキルを持つ人に活躍の場が広がっています。
 Oさん
Oさんまだデータドリブンの取り組みはスタートしたばかりです。ですから、データ分析よりも手前の、データを集める基盤を作ったり、各部署の業務理解を深めたりと、様々な経験ができると思います。我々の部署としての業務や在り方も、一緒に考えていけると思います。データサイエンティストという職種以上の経験をできるのではないでしょうか。
 Tさん
Tさんお二人が言うように、NSKのデータドリブンはまだ始まったばかりです。だから、データから何かを発見する際にも、初歩的な気づきであっても価値創出の一歩に繋がっていきます。新しい組織なので、一緒に新しい価値を生み出していけたら嬉しいですね。
※組織、役職名称は取材時のものです。